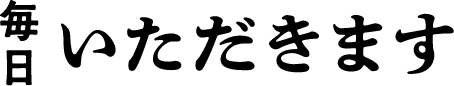<ご報告>【地産地食の学校_17】菌ちゃん先生のおはなし会
「食と農から考える、子どもたちのからだづくり」
2019年10月21日(月)

- 場 所
- 神山町 農村改善センター
- 日 時
- 10月21日(月)18:00~19:30
◆案内人
“ 菌ちゃん先生” こと吉田俊道さん
◆参加費
大人(18歳以上)¥1,000
お子さまもぜひ一緒にご参加ください。
【地産地食の学校】は、農業や食にまつわる案内人をお招きし、その方々が学びの「案内人」となる食育学校です。今回は、Food Hub Project メンバーの大東、樋口に加えて田中泰子さん、植田彰弘さんの4名の共同企画で開催しました。
案内人
“ 菌ちゃん先生” こと吉田俊道さん

【プロフィール】よしだ・としみち / NPO法人大地といのちの会理事長・菌ちゃんふぁーむ園主・農学修士。1959年 長崎市生まれ。九州大学農学部大学院修士課程修了後、長崎県の農業改良普及員に。96年、県庁を辞め、有機農家として新規参入。99年、佐世保市を拠点に「大地といのちの会」を結成し、九州を拠点に生ごみリサイクル元気野菜作りと元気人間作りの旋風を巻き起こしている。2007年、同会が総務大臣表彰(地域振興部門)を受賞。2009年、食育推進ボランティア表彰(内閣府特命担当大臣表彰)。長崎県環境アドバイザー。主な著書は「生ごみ先生の元気野菜作り超入門」「菌ちゃん野菜作り&元気人間作り」「お野菜さんありがとう~子どもと一緒に元気野菜作り」
“菌ちゃん先生” こと吉田俊道さんのお話を聞いて、自分たちがすぐにできることや次の世代を担う子どもたちのために今大人ができることを、それぞれの立場から考えられる時間が過ごせるといいなぁと思います。
テーマ「食と農から考える子どもたちのからだづくり」

内容
主催メンバーより
カメラマンの植田彰弘です。
神山町で農業(主にお米と野菜)に向き合うきっかけとなったのが「里山の会」という有機栽培グループとの出会いでした。”自分たちの家族や孫世代の子供たちに安心な野菜を食べさせたい”会の理念をはじめ、70代前後のお父さんお母さんが有機栽培に向き合う姿勢に感銘し、入会を決め農業を愉しんでいます。自分自身、農と向き合う中で”有機栽培”や”自然栽培”は本当に安心なのか?という疑念を覚え始めました。地域や人の捉え方で栽培方法はいくらでも確立でき発信できる今だからこそ、その枠に捉われず、農業を通じてどんな社会や幸せを築きたいかを考えていきたいと思っています。農業というからには、生業としての考えも必要です。これから先の未来、子供からお年寄りまで多くの人が「人を想い栽培される食べ物の在り方」を学び合い、感謝しあえる場所を作っていくことに大きな意味があるように感じています。そして、〇〇栽培という枠で、栽培方法を確立することなく、土やそこに凄む生物を考えた”農の在り方”を正しく理解し、僕が所属する里山の会のみなさんと一緒に学んでいきたいと思い、吉田先生のお話を伺いたいと思いました。
フードハブ・プロジェクトの農園係/八百屋係の大東です。
有機栽培で野菜を育て、料理人と関わりながら、食育活動で子どもたちと関わりながら、畑からテーブルまでのつながりを感じられる取り組みを心がけています。それぞれに日常や、専門性や生産性に忙しく、世界はどのようにできているのか感じにくくなっている気がしています。そこで、畑に集まり、菌ちゃんたちと土や野菜を感じて、誰かや何かや菌ちゃんたちが育んでくれる世界への想像力が広がっていけばいいなと思っています。あわせて自然のいきいきとした美しさや営みを五感で感じられる「場」を作っていきたいと思っています。そして家庭菜園や、それぞれの集まりでやってみよう、というとっかかりやそのベースづくりができたら。自分自身で体づくりをしていく、畑や日々の暮らしや、地域も手作りしていく、それがよろこびとなればいいな…と思っています。吉田先生の話をお聞きすることで、その豊かさと視野の広がりを感じ、何を選択するのか、みんなでこれからのことを考えていきたいと思っています。
4歳のこどもの母親、田中泰子です。
これからの季節に心配なのが、感染症。発症すると一気にこどもたち、そしてその兄弟、親たち、そして時には先生方にも感染が及んでしまいます。それを受けて、いつもの暮らしがこどものちょっとした変化に敏感にならざるを得ない日常が生まれます。以前、吉田先生のお話をTOECでお聞きし、整えるのは、実はまず子供たち自身の身体であり、家庭の食卓(食事)であり…、それが自分たちの住んでいる神山でなら、畑で野菜を作っている人たちが多いこの地域でなら、地域に暮らす人と共に考えていける可能性があるのでは…と思い始めています。家庭や地域でできた元気な野菜をこどもたちが食べ、そして、感染症などにも負けない元気な身体になっていく。こどもだけではなくて、高齢になった方たちも元気になっていく。そんな町づくりが出来ればと思い、一人の母親として、先生のお話を伺い、次のステップへとつなげられるよう、考えていきたいと思っています。
お話会参加者の感想
18時から始まった前半の部にご参加くださった方の感想を一部紹介します。
「菌ちゃん先生のパワーに圧倒されつつ、菌のこと、一人ひとりの意識のあり方について丁寧に教えていただき、多くの学びがありました」
「循環の最初からしっかり理解しないと、間違った判断が起こりうると気づきました。神山で保育園の食育から子どもを元気に、大人も元気につながるようなことができればと思うけれどどこからできますかね」
「有機農業は『命の大切さ』を学ぶことにつながるということ、すべてのことに役割があるということが印象的でした」
「地球と菌のつながりを知れたし、その循環に感銘を受けた。この考えた方を自分の中に落とし込んで、農業や体のことにやっていきたい。そして人に伝えたいと思った」
「土作りには時間がかかると少しあきらめていましたが、やる気になりました」
「研究に裏付けられた藩士に笑いも挟みつつ、すごく惹きこまれておもしろかった。すぐに実践できるものも多く、とてもためになりました」
「草には草の意味があると共生を目指して野菜を作ってきました。だから『草と共に』は嬉しかったです。うちは草の根っこも使って発酵させて生ゴミも土になって土地にかえす循環をしています。もっとこの考え方が広がっていくことをのぞみます」
「いのちの生きる海をつくっていくには、どうしたらいいのだろうかとー。植物プランクトンが生きる海をー」
「難しいことを分かりやすくテンポよく楽しく聞くことができました。畑の話も食の話も納得。少しずつできることしたいです」
「有機農業、プランターでもできるとお聞きしたので、我が家でも実践したいです」
「広範囲に渡る興味深いお話が伺えてよかったです。実家周辺の耕作放棄地(棚田)の土をよみがえらせるということを、春までに取り組んでみたいと思います」
「生きているものは、元気なものには菌が付かないというのが感激でした。地球の生命循環の要である菌のめぐみをより理解して、めぐみを受け取って生きてゆきたいです。プランターから始めます」

後半の部は、より実践的な有機農業について質疑応答の時間をとっていただきました。その場はまさに、集まった人たちと一緒に考える場、お互いに学び合える場、「農業」についての勉強会の場でした。集まった人たちの熱量に驚きつつ、帰り際に「今度(神山町に)来るときには何か始まっているといいね。」と吉田さんがおっしゃっていたように、企画メンバーでも「この感じ、つなげたいよね」と話しています。
Food Hub Projectでも、農業や農、食について、言葉を交わせるような場をつくっていきたいなぁと話しています。
当日の配布資料にもあった吉田先生のブログはこちらです。ご覧ください。