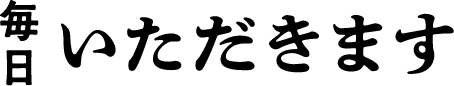2022年1月8日(土)
神山大豆、収穫!

今年は広野小学校でも神領小学校でも大豆を栽培しました。大豆の種は、町内の畑で毎年栽培されている門田さんから分けてもらいました(昨年、下分保育所でも栽培した大豆です)。
種まきは6月後半の2日間(連日)で実施しましたが、生長の様子は広野、神領の2つの小学校で全然違っていて…広野小学校の大豆が先に収穫され、その2週間後に神領小学校の大豆を収穫。こんなに違いが出るのかー!生長具合の比較をしてもおもしろかったかも!?と今更ながら思っています。
3年生の国語の教科書には「すがたをかえる大豆」という説明文が載っています。豆腐、納豆、油揚げ、味噌、醤油…など大豆の加工食品は私たちにとって身近ですが、それがどのような過程を経てすがたを変えていくのかが説明されており、大人も読むと勉強になる、おもしろい内容です。
一粒の種からニョキニョキと芽をだし葉を出しワサワサと茂ってくる様子、鞘がぷっくりと膨らんでくる様子、カメムシが遊びにきたり、緑の葉が茶色く変化していく様子、根の張った茎を「うんとこしょ!」と引き抜くときの感覚、鞘から出したばかりの大豆の味…。子どもたちが畑で五感を働かせ、めいっぱいその感覚を味わっている姿を見ると、こちらもうれしくなります。

引き抜く時には力を合わせて…!(神領小学校)
一足先に収穫していた広野小学校の大豆は、振るとカラカラと音がしていました。鞘から大豆を取り出し重さをはかったら3kg30g。もとの種は手のひらに乗るくらいの量だったのに!「生まれた時の赤ちゃんと同じくらいだね」とつぶやく3年生。ようこそこの世界へ、大豆。

鞘から大豆を取り出すには、叩きつけるのがいいみたい(広野小学校)

重さをはかったら3kg30gでした(広野小学校)
農林水産省の資料によると、大豆全体の需要量は中期的に増加傾向で推移しているそうで、そのうち、国産大豆はほぼ全量が豆腐、煮豆、納豆等の食品向けに用いられるそうです。また、食品向けに用いられる国産大豆の量は、前年度より1,000トン増加しているとのこと。(「大豆をめぐる事情」令和3年11月 より)
国産大豆の自給率はわずか7%(食品用に限ると25%)。3年生の子どもが「これは国産大豆だから貴重なんだ〜」と言っていましたが、その貴重な大豆がどんな風にすがたをかえるのか、楽しみ。じっくり味わいたいものです。