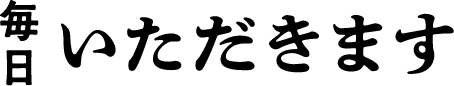2017年3月13日(月)
フードハブに込められたふるさとへの想い

神山町では、高齢化と後継者の不足による耕作放棄地の増加が大きな課題となっています。
近年、サテライトオフィスや移住者が集まることで注目を浴びている神山町。しかし、50年以上にわたって、その人口は減り続けてきました。その間、地元に踏みとどまり、社会と産業、そして文化を担ってきた世代がいます。そして今、急速に彼らの引退が始まっています。
その影響は、単なる地域人口の減少に留まりません。地域の限界が迫っています。
ここに暮らす人たちがこれからも豊かに暮らしていくためには、どうすれば良いのでしょうか。フードハブ・プロジェクトの農業指導長の白桃茂が話します。

雨の中、もち米の植え方を指導するフードハブ・プロジェクト農業指導長の白桃 茂
「生産者がいなくなったら田んぼにしろ、1、2年荒らしてしもうたら元に戻すのに3、4年かかるんです。本当に元に戻すのは何年もかかるからね。今が限界かなあと思うんです。僕の親の代が辞めていきよる時代やから。今、支配人が思いよるやつ(フードハブ・プロジェクト)がちょっと遅いぐらい。でも、まぁどないか間に合うかなぁ」
地域の農業を次世代につなぐ仕組みづくりを目指して、Food Hub Project(フードハブ・プロジェクト)は生まれました。
農業という選択

農園長の徳元。食堂のかま屋の前にある「つなぐ農園」にて。
農園長としてフードハブ・プロジェクトに加わった徳元。新聞記者の頃から中山間地域の活性化をテーマに掲げていました。
「日本の中山間地って日本の問題の縮図というか。介護問題にしてもそうです、一次産業の問題にしても、雇用もそう、日本で出てくる問題・課題が先に出ている。それを放置しとくと取り返しのつかないことになっていくんじゃないかという思いがありました」
中山間地域を取材する中で、当事者になり切れない自分にもやもやを感じ始めたといいます。
「傍から見て事実を書いているだけでは、評論家に過ぎないんじゃないか、小さいことでもいいので現場に立って、実例を示していった方がいいんじゃないかっていう考え方に変わってきました」
もともと農業に興味がなかったという徳元。
新聞社をやめてからは海外へ。
イギリスやニュージーランドなど、あちこち旅行をしたといいます。
「 ニュージーランドで南島を周遊していた時に、ユースホステルでポスターが貼ってあったんです。そこに英語で『 これ以上の発展は人類に必要なのか』ってメッセージがあって。
目先の、短期的なお金儲けをして、それで自分が満足できるのか。次に就職するときはお金儲けだけじゃなくてライフワークとして取り組める何かを選ぼう、と。
それを実現する手段は農業が一番近いんじゃないかという考えがあって今につながってるんです」
徳元は、「 農業をやることがどういう風に社会をよくしていくのか」を実践するため、地元徳島市で農薬や化学肥料に頼らない自然農法の畑を営み始めます。
その後、見聞を広めるため、農業研修で訪れたフランスで目にしたのは、小規模ながら生き生きとした農業でした。
「フランスに行って、安全でおいしい食べ物を作る苦労とそれを食べる喜びを自分たちで体験できるっていうのが、本当の豊かさなんじゃないかなって思い始めて。すごい楽しそうやなと思ったんですよね。
リンゴを使ってシードルというお酒を作ったり、天然酵母のパン作ったり。 なんでもお金で買うんじゃなくて、地域にある資源を上手に使って、すごい豊かな生活を送ってるんですよ 」
この体験をこれからの農業経営にどう活かしていこうかと考えてた時期に、Facebookでフードハブ・プロジェクトの募集記事を見つけます。
「 不特定多数の人を相手に商売するんではなくて、特定の人に野菜やサービスを提供するというイメージを持たないと、これからの商売は規模の大きいところに勝てないんじゃないか、特に、僕みたいに零細農家は。
そう考えていた時期だったので、考え方が一致してるフードハブをちょうど知って何か面白いことができそうだなと思って」
後継者不足に悩まされている神山町。
地域でお金が回る仕組みをつくることが、今まで追っていた中山間地の活性化にもつながると、徳元は考えています。
「 農業で稼げてる人っていうのはやっぱり資本のある人。だから中山間地でなんとか生計を成り立たせる仕組みも作らなければいけないんですけど、そんなにすぐにできるもんではないかなと。
料理人が関わったりとか、教育者が関わったりしてる意味はそこにあるんかなと思ってるんです。僕はまず野菜を作るのに専念して。僕一人でできることって限られるんで、ちょっとずつ皆を巻き込んで行きたいなと思ってるんです」
自分で食べる分くらいは自分で作る。
そんなところから始めて欲しいといいます。
「最近は、割と食事を疎かにする人、多いじゃないですか。そこが孤食や化学物質過敏症など、いろんな問題の原因になってるんじゃないかなって思うんです。
鍋会とかそんなんでいい、食材を持ち寄って一緒にご飯食べるとこから始めたらいいと思うんです。そっからちょっとずつあんなことやってみようかという動きが出てきたらいいなと。
自分で作らんかったらコンビニ行くか、ファストフードや牛丼屋に行くかしかないじゃないですか。みんなでシェアすれば半額以下で、新鮮で栄養たっぷりなおいしいものが食べれると思うんですよね。その贅沢を皆に知ってもらいたいですね」
きっかけは、ひとつの出会いでした

フードハブ・プロジェクト農業長 白桃
現在はフードハブ・プロジェクトで農業長を務める白桃薫。彼には危機感がありました。
「うちの親父が倒れたんですよ。それがちょうどお米の収穫の時期で。うちの親父、町内でお米やってる割合か大きいんで、地域のお米の生産が止まってしまったんですね。皆パニックみたいに困ってしまって。役場の人たちからも”白桃ショックやな~”て米騒動みたいな感じで言われて。
親父が当時55歳で一番の若手、一人崩れただけで町の米の生産が止まる。それってリアルだったんですよ。自分の親父が倒れただけでこういう状態になるから、無理が出てきてるんやろなとか、助け合える仕組みがないとか、次の世代がおらんとかっていう危機感をその頃から少しずつ感じ始めとったですね」
そんなとき、神山町の地方創生戦略のワーキンググループが発足します。
白桃が所属したのは、食の循環について考えるグループでした。

2015年7月から12月末まで行われた、神山町創生戦略を考えるワーキンググループでのひとコマ
ここで神山町の住民として参加していた現フードハブ・プロジェクトの支配人の真鍋と白桃が出会います。
「自分たち農家の農業に対する目線って、いかにこれを高く売ろうかとか、作って売るって行為だけを見る目線だったんです。でも、真鍋が見てる目線って、アプローチが完全に違っていて。仕入れて調理して食べさせる、料理人から見た、 ほんと反対から見てる感じだったんですよね。
目線は違っても芯になる部分は一緒の思いで、真鍋の活動と自分が思ってる物事ってつながってるんだなと思って。見る方向が違っても同じ価値観がある、そこがすごい大きかったですね」
そして白桃は、構想段階だったフードハブ・プロジェクトを「役場をやめてでもこの事業をやりたい」と手を挙げたのでした。

白桃 薫の父、茂。農業指導長としてフードハブ・プロジェクトに参画
「そうやね真鍋さんと薫が出会ったことから始まった感じやもんね。ほなけん何でも一緒なんやろうけど、出会いが大切で。子供も役場行きよったのに結局ああいう形でするってのはなんかあったんやなとは思っておったんです。
辞めてまでしますと言われて、お婆さんなんか特に『 辞めたらあかんで!』言うてぶつぶつ怒りよったけど(笑)。ほなけど、僕は、真鍋さんと一緒にカリフォルニアの農場やを見に行って惚れたのかもわからん。なんて言うんかいな、子供が懸けた意味が分かったし、この出会いを大切にしてやらなんだらいかんなぁと。うん、思うたんです。
今まで僕がしてきたことを活かしてくれよるとこもあるんです。そういう面でも手伝えるかなぁと。今まで一生懸命したことが活かせるんやったら思うてるんですけどね」

2016年1月末、会社設立前に初期メンバーで訪れたカリフォルニアの農業と食文化のスタディーツアー。カリフォルニア、バークレーにあるChez Panisseというオーガニックレストランと長年契約して野菜を育ている、Green String Farm の農園に立つ白桃親子。ここで白桃父が「神山の昔の農業の景色ですね」との一言が今でも印象に残る。
白桃の「役場をやめてでも」という志に、移住者が応え、そしてまた神山の人々が勢いづいていくつながりが生まれたように感じます。
茂さんは、当初、フードハブ・プロジェクトについてこう考えていました。
「真鍋さんに聞いたんです。なんの為に仕掛けたんかって。会社として入ってきとるから、どういう形で始めとんか聞いたんやけどね。普通、会社で入ってきたら損得があるでしょう。それが引っかかってたんです。一番肝心なことやと思って。
ぱっと逃げて行こうと思ったら逃げていけるもんな。でも、ほうでもないような話するし、真面目に話をしようとするけん、これは一生懸命せなんだいかんな思ってね」
地元の想いや取り組みに応えて、外から入ってきた人々に地元の人が加わる過程で、地元の価値を共有する循環が生まれています。
「今まで、親の代から70年超えてずーっともち米を作っとって。毎年、毎年種蒔いて、美味しいんて言うんだから何気なく作りよったんです。ほんで真鍋さんと話よったら、それ宝物ですよって言われて。ああ、そうなんやなぁと。
ただ毎日、毎日してきたことが宝物と思わしてくれた。見出してくれるんやなと」
地域で暮らしを営み、農業を守る

2016年10月の鬼籠野での餅米の収穫の様子
昔の神山町であれば、大半を自給していた食も、今や外部依存がとても高くなっています。
地域から、食の循環が失われつつあります。
「うちの米の現状っていうんは、受委託。それも割に合わんようになって、お客さんの田んぼが知らん間に、自分が田植えして、生産の方に入ってしまったんよね。
今ほとんどヨソの田んぼばっかり。知らん間にこんな形になっとって。世の中そういう流れになっとんか、損得で考えてするようになってくるし、割に合わない、歳もあるし家の事情もあるし、で田んぼ渡されてね、知らん間に増えてしもうて。口空けてる人ばっかりやしね。
世の中の仕組みが分業化してる。何のために仕事をしてるのか、皆分かってないとこがあるよ。基本は食べるためやろ。」
日々の食は自分たちで働き、自分たちの大地から生み出す。
そして、自分たちが日常的に使っていく。
本来、暮らしとはそういうものなのではないでしょうか。
暮らしを営むこと。
「お米の値段は上がってこないから損得考えたらアレなんやけど、まぁ自分が農業好きやから。育ててお米になって、ほいでお客さんが美味しいって言うてくれるんやから。辛抱が、辛抱とは思わん。天職かいなと思って」
自分がいるからこそ地元の人が美味しい食事ができるという、自信と誇り。
そして、つながりの実感。
「今年初めて父親に米の管理の一部を任されたんですけど、皆に食べてもらっておいしいとか、自分が作ったものが認められるときの瞬間。やりがい、あるなあと思って。すごいうれしかって。
昨年も、会社のパーティーでお世話になった人たちに食事を振る舞って、最後に『 今日一番何がおいしかった?』 って真鍋がお客さんに聞いて、『 おにぎりがおいしかった!』ってみんなが言ってくれて、すごいうれしくって」
言葉に込めたこの実感で、地域を、そして農業を支えていけたら。
自然の中から、そして人と人との繋がりの中から、「手」でつくり出すこと。
それこそが私たちフードハブ・プロジェクトが目指す「豊かさ」です。